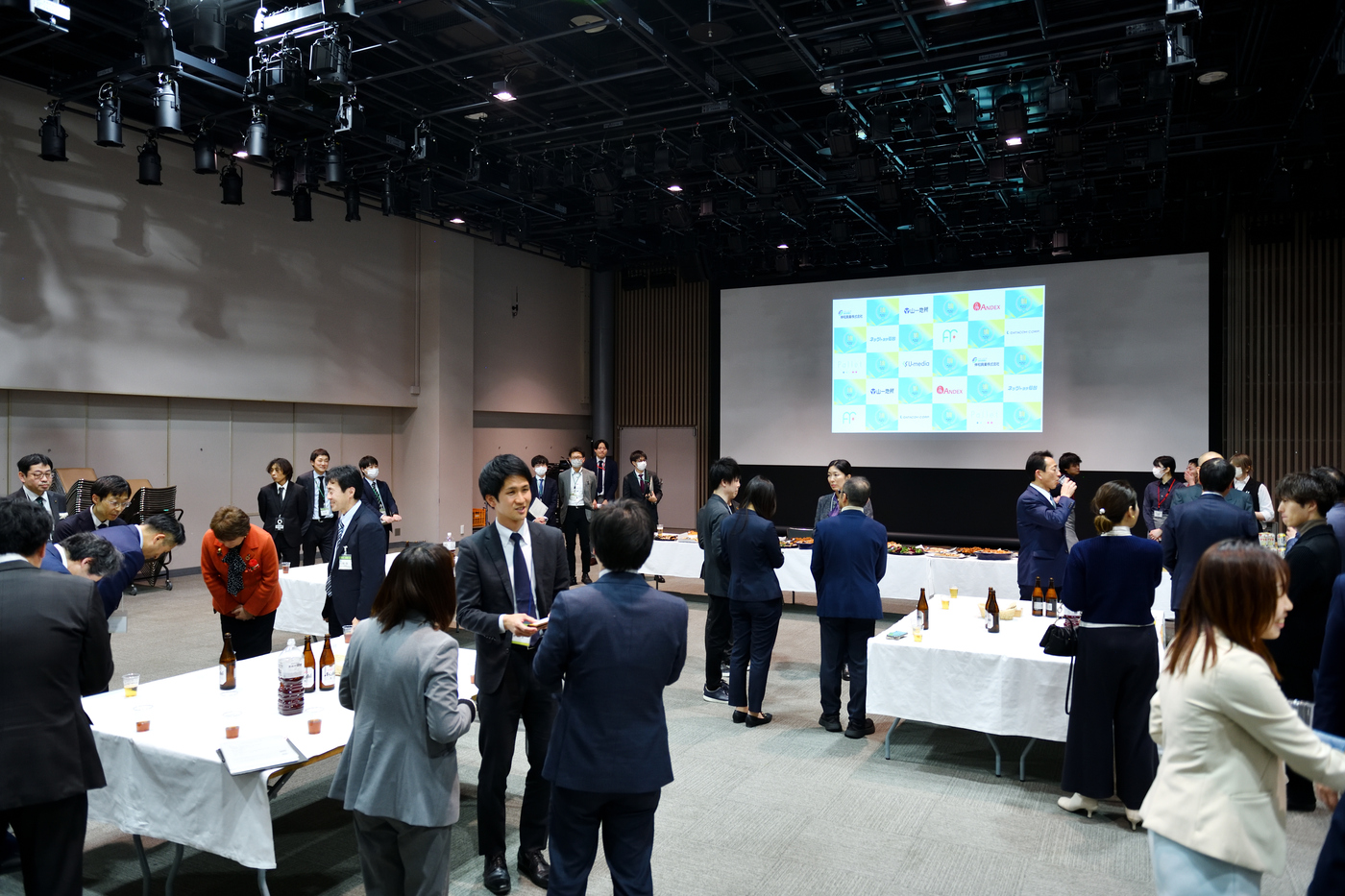HOME / NEWS / 「SENDAI NEXT VISION 地域未来創造フォーラム~多様な人材活用による企業成長に向けて~」レポート
お知らせ 2025.03.29

2025年2月6日、「SENDAI NEXT VISION 地域未来創造フォーラム」がエル・パーク仙台スタジオホールにて開催されました。
仙台市では、人口減少が見込まれる中、多様な人材の能力を最大限発揮することで、企業の成長につなげるダイバーシティ経営を推進しています。同フォーラムでは、働く「人」に焦点を当て、ダイバーシティ経営をテーマとしたプログラムや、多様な人材が活躍できる職場づくりと若者にも関心の高い社会課題解決に向けた取り組みを表彰する仙台「四方よし」企業表彰(2年に1度開催)を実施。
当日は、外国人材を活用したダイバーシティ経営で成長を続ける、スズキハイテック株式会社代表取締役社長・鈴木一徳氏による基調講演、仙台「四方よし」企業表彰の入賞企業8社が登壇し、さまざまな取り組み事例やその成果を紹介するプレゼンテーション、各賞の表彰式が行われました。イベントの様子や受賞結果についてレポートします。
近江商人の経営哲学の一つとして広く知られる「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の「三方よし」に、従業員にとって魅力的な職場である「働き手よし」を加え、人手不足の解消とそれに伴う企業の持続的な成長を目指す仙台「四方よし」企業制度。
それに取り組む企業の中から、事前審査を通過したファイナリスト8社が、自社の「四方よし」な取り組みについてプレゼンテーションを行いました。
審査委員を務めたのは、東北学院大学地域総合学部政策デザイン学科教授・和田正春氏、経済産業省経済産業政策局経済社会政策室室長・相馬知子氏、株式会社七十七銀行地域開発部部長・鈴木恭子氏、仙台市経済局局長・木村賢治朗氏の4名。一社ごとに審査委員の講評を交え進行しました。

1社目の発表は、企業の組織開発や人材育成、地域共創事業を行う株式会社Pallet代表取締役の羽山暁子氏。
同社では、事業成長に向けた必要な人財確保に課題を抱える中小企業と、魅力的な職場がないことを理由に県外転出をしてしまう働き手のミスマッチを解消すべく、①働く人たちのエンゲージメントの向上、②東北の企業における人事機能の適正化、③女性が活躍できる環境の整備、3つをテーマにステークホルダーとともに多様なプロジェクトを立ち上げ活動しています。
その取り組みの一つとして、産官学連携で東北の企業の魅力を高めていく「東北・人事リデザインプロジェクト」を紹介。先日、キックオフイベントが開催され、有識者による講演、各企業の取り組み事例の共有、対話の場づくり等を行っているとのことでした。
さらに、同社の社員一人ひとりのやりたいこと「will」とライフスタイルを尊重し、働き甲斐を感じながら成果を最大化する独自の「WiLL-basedマネジメント®」を実践。お互いを尊重し合って働ける仕組みを導入しています。
同社の発表について、審査員からは「willへの着目などチャレンジングな取り組みは、若い世代にとって一つのモデルになると思う。実践したことをお客様に還元し、東北で働く人の幸福度を高めてほしい」との講評がありました。

2社目の発表は、「ひととちいきのミライをゆたかにする」をパーパスに掲げるコミュニケーションデザインカンパニー、株式会社ユーメディア代表取締役社長の今野均氏です。「世間よし」の課題として、杜の都のシンボルロードである定禅寺エリアの求心力の低下を挙げました。同社は、仙台市中心部の回遊性を高めるため、地産地消をキーワードに地域と共創した3つの主催事業(仙台オクトーバーフェスト、バル仙台、仙臺横丁フェス)とその成果を発表。
また、2009年から進めてきた働き方改革をさらに一段階上げ、挑戦と変革のカルチャーを醸成するために「働きやすさ」と「働き甲斐」をセットで高めることに注力。活発なコミュニケーションと独創的な発想を可能とするオフィスリニューアル、独自の研修体系による社員育成等に取り組んだ結果、女性管理職比率17.6%、障害者雇用率3.6%、育児休業取得率100%、若手社員による新規事業の創出といった成果が上がっていることを紹介しました。
審査員は「若者が仙台から首都圏に出てしまう歯がゆさがある中、首都圏に負けない魅力を持つ点は、UIJターンを推し進めるためのヒントになる」と講評を述べました。

3社目の発表は、新車・中古車の販売等を手掛けるネッツトヨタ仙台株式会社代表取締役副社長・守川雷太氏です。自動車ディーラーという男性社員が多いイメージの業種でありながら、女性同士の横のつながりを後押しし、女性活躍を積極的に進めるなど、従業員の声を生かした経営と制度の拡充によりダイバーシティ経営を展開しています。また、子どもや若者の育成支援や自然保護活動、魅力的な職場環境づくりの取り組みを紹介。顧客会員制度「そらっこくらぶ」における親子体験型イベントや、学生に向けた活動体験の報告、東日本大震災で失った防風林の再生活動などは、一過性ではなく継続して行っている点が特徴です。
審査員からは「一度何かをやろうと話が出ても、息長く続けることは難しい。自動車に関わる仕事をする中で、地域とつながり持続的に取り組むことで、この先なにが生まれるのか、とても期待している」とコメントがありました。

4社目の発表は、仙台市に本社を置くIT企業、データコム株式会社取締役の小野寺裕貴氏です。データコムは、スーパーマーケットをはじめとする小売業にデータ分析のシステムを提供しています。プレゼンでは、時差出勤、時間休暇、在宅ワークなど、働き方の柔軟性を高める各種制度が社員にとって利用しやすく運用されていることで、働きやすさと効率性を両立した取り組みになっていることや、外国人材の活躍が日本人社員のマインドを引き上げる社内の好循環について発表。「InternationalなTalentが活躍するIT企業に向けて事業を展開していきたい」と話しました。
また、「世間よし」についてはフードロスへの取り組みを発表。同社はスーパーマーケットと仕事をする中でフードロスへの課題感を強く意識し、地域の企業やスポーツクラブと連携し1年間で100kgにおよぶ食品の回収・寄付を実施しています。
審査員からは「現在行っているフードドライブ活動から本業であるデータ活用による課題解決へとさらに発展することを目指しており、今後の取り組みに期待が持てる」と講評がありました。

5社目の発表は、障がい者をはじめとする社会的弱者を納税者にすること、働ける能力がある弱者に職場を提供し、やりがいや生きがいを見出してもらうことを目指し、ダイバーシティ経営を精力的に推進している株式会社アップルファーム代表取締役の渡部哲也氏です。
アップルファームはあらゆる人が活躍できる仕事を創出するため、人に組織が合わせるという発想でビュッフェレストランや農業、福祉施設など様々な事業を展開しています。「社会課題が社会課題を解決する」をテーマに、障害者雇用のコンサルティングや企業への講演活動も積極的に行っています。
また、同社では、個人の可能性を信じてチャレンジを促進することや、それぞれの長所を見つけそれに合わせたマッチングで自己肯定感を高めるなど、挑戦とケアのバランスも大切にしています。
審査員は「行政の立場では障がい者は福祉のイメージが強いが、経済面を含めて自立を中心に据え、成立している。社会課題に対する一つの答えだと感じた」とコメントしました。

6社目の発表は、建設業を営む伸和興業株式会社の総務部長・平博行氏です。プレゼンでは、建設業界のイメージを変えるさまざまな取り組みが紹介されました。
水害を機に本社を移転した同社は、社会貢献を念頭に、地域住民の避難スペースや備蓄倉庫、仮設トイレなどを備えた新社屋を建築。さらに、業界では珍しいフレックスタイム制を導入し、柔軟に修正しながら活用を続け、新卒採用につなげました。自社に限らず、協力業者でも男性社員が多数を占める状況ではありますが、女性技術者のために女性用トイレや更衣スペースも整備。ストレスチェックでメンタル面もサポートするなど、3Kのイメージを払拭し、新4K「給与・希望・休暇・かっこいい」の実現に向け励んでいます。
審査員からは「フレックスを導入するだけでなく、活用できるよう修正しながらトライを続けるところを評価したい」、「震災を経験した者として地域のための避難環境を用意してくれるのはありがたい」との意見が上がりました。

7社目の発表は、不動産業を展開する株式会社山一地所総務部総務課の佐藤浩一氏です。同社は、少子高齢化による社会課題への継続的な取り組みを発表。衰退・減少傾向にある地域社会の伝統や文化の担い手不足解消に向け、自治体や町内会と連携して地域イベントや祭事に参加。現在は年間10以上のイベントに延べ150人以上の社員が自発的に参加しています。また、地域住民と行政の財産を守るために、資格と実務経験を備えた社員が不動産相続セミナーを行うなど、地域と歩む同社ならではの事例を紹介しました。
さらに、新社屋の建設をきっかけに事務所を一ヶ所に集約し、社員の意見をもとにお客様や働く社員が「来たくなるオフィス」を目指し、職場環境を整備。ソフト面では、アンケートや定期的な職場巡視で出た社員の意見を上層部まで吸い上げるボトムアップの仕組みを構築し、自身の意見が施策に反映されることで、当事者意識の醸成、離職率の低下というプラスの効果があったと説明しました。
審査員は「組織として働くには、全員が同じ方向を見て同じ意識を持つことが大切であり、それができている。ボトムアップの取り組みも良かった」とコメントしました。

8社目の発表は、ソフトウェア開発やウェブシステムの設計、通信事業などを行うアンデックス株式会社代表取締役の三嶋順氏です。同社では、東日本大震災の津波被害を機に、IT技術を活用した社会貢献事業に挑戦。宮城県の基幹産業である水産業の課題に着目し、現場で漁業関係者とコミュニケーションを取りながら、海水温度や栄養分、酸素量をスマートフォンで確認できる「海の可視化」システムをつくりました。また、社員にアンケート調査を行い、社内改善委員会を通じて上層部に伝える仕組みを構築。従業員規定を毎年見直すなど、職場環境の向上にも積極的です。
ダイバーシティ経営に関する取り組みでは、外国人社員の採用と活用について紹介。同社は2020年より外国人採用を行い、現在は計5名を採用。採用にあたっては、長期インターンシップを導入し、入社後のミスマッチをなくすべく企業と学生の相互理解に努めています。
審査員からは「ITはパソコン上の仕事というイメージが覆され、海の可視化に生かされると知って勉強になった。社員の不満にも向き合う姿勢に本気度を感じた」と評されました。

第二部は、山形市で金属めっき加工事業を展開するスズキハイテック株式会社の鈴木一徳氏を講師に迎え、「ダイバーシティ経営で企業を成長させる秘訣~創業110年の老舗企業が語る変革と成功~」と題した講演が行われました。
同社は、海外進出を機に外国人材の採用を始め、現在は従業員の約40%に当たる93名を雇用しています。鈴木氏は動画を交えながら、外国人材の採用に至った背景、手段、その効果などについてスピーチ。外国人と日本人がお互いを尊重・理解し、働く価値や目的を共有することの重要性と、サポート体制の必要性について訴えました。また、外国人材の採用によって社内の風土や研究開発等に好循環が生まれたことにより、2015年には16億円まで落ち込んだ売り上げが2022年以降は過去最高を更新し続け、2024年には42億5,000万円と驚くほどのV字回復を遂げました。「外国人材がいなければ成長はなかった。ダイバーシティは目的ではなく手段である」ことを強調しました。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
講演後は、外国人と働く上でのポイントやマネジメントなどについての質問もあり、一人ひとりに合わせたコミュニケーションの重要性を説くなど、興味深い内容となりました。

第一部の公開プレゼン審査を受け、4名の審査委員が大賞・優秀賞・ダイバーシティ経営特別賞を決定。第三部でその発表と表彰が行われました。
ダイバーシティ経営特別賞は、障がい者の就労支援や就労機会の拡大に積極的に取り組む㈱アップルファームが受賞。単なる障がい者雇用ではなく、自立性を高め、さらに収益性を追求する優れたモデルを構築していること、自社の成功事例やノウハウを積極的に啓蒙することで、社会課題解決に向けた取り組みを加速化していることが受賞につながりました。

優秀賞には㈱山一地所と㈱アップルファームの2社が選出。山一地所は、地域・顧客とのつながりを大切にする地域イベントや不動産セミナーを社員が自主的に継続して取り組んでいること、ボトムアップによる吸い上げの仕組みが、モラルの向上、当事者意識の醸成に繋がっていることが受賞理由となりました。㈱アップルファームはダイバーシティ経営特別賞に続く二冠です。


そして、大賞に輝いたのは㈱ユーメディア。地域の資源とイベントを組み合わせ、新たなまちづくりへの試みを持続的に行い成果を上げていること、多様性を単なる属性ではなく「知と経験」にまで広げて捉え、多様な経験を持つ社員が中核で活躍し、新事業を創出していることが高く評価されました。


表彰式後はギャラリーホールに場所を移し、参加企業による交流会を開催。今後につながる情報交換や、コミュニケーションの場になりました。