HOME / NEWS / 令和6年11月28日開催「地域政策デザイン実践セミナー」開催レポート
お知らせ 2025.03.14

仙台をより魅力ある地域とするため、地域社会の発展や市民生活の向上に寄与する市内中小企業の優れた取組みを紹介・表彰する、仙台「四方よし」企業制度。「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」の三方よしに、社員にとってより良い職場環境づくりに取り組む「働き手よし」を加えた「四方よし」な企業として、社会課題解決や魅力的な職場環境づくりに向けた取組みを後押ししています。
東北学院大学五橋キャンパスで開催された本イベントは、「仙台『四方よし』企業制度」と仙台の魅力的な企業を地元学生に知ってもらうことを目的に実施されました。Part1では行政から仙台「四方よし」企業制度開始の経緯や役割の説明、Part2では仙台「四方よし」受賞企業による自社の「四方よし」な取り組み紹介、Part3では実際に学生が仙台「四方よし」受賞企業を訪問し、取り組みを取材した結果の発表が行われました。
東北学院大学地域総合学部政策デザイン学科 和田教授と仙台市経済局 猪狩産業政策部長が登壇。Part1では、はじめに仙台市の猪狩部長より「仙台『四方よし』企業制度」のねらいが説明されました。「仙台は東北各地から学生が集まる一方で、卒業と同時に仙台を離れる学生が多く、若手人材が流出している課題があります。そこで、学生に仙台の魅力的な経営者や職場についてもっと知ってもらうため、そして社員が生き生きと働く中小企業の取組みを広げ、地域の活性化につなげようと平成28年度に〈仙台『四方よし』企業制度〉がスタートしました。〈仙台『四方よし』企業制度〉は、売上高や納税額だけではなく、働く側にとってのやりがいや充実感を企業の評価基準とする仙台市独自の取り組みです」と説明がありました。和田教授は「企業の質的要件を明確に示して発展を応援する行政の取り組みはとても貴重。ここから新しいモデル企業が生まれたらすばらしい」とコメントしました。

Part2では、仙台「四方よし」受賞企業3社による自社の「四方よし」な取り組み紹介が行われました。
「秋保ヴィレッジ」が地域に新たな風景を
《お茶の井ヶ田株式会社 代表取締役 井ヶ田健一氏》

「お茶の井ヶ田株式会社」は、秋保地区にオープンさせた「秋保ヴィレッジ」での取り組み等が、農業者支援や地域の賑わい創出、観光振興等の様々な面で地域課題の解決に大きく寄与している「世間よし」として高く評価され、平成28年度に「仙台『四方よし』企業大賞」を受賞しました。
井ヶ田グループは1920年創業、宮城を中心に東日本で約50店舗を展開する老舗企業です。「お茶の井ヶ田株式会社」では、茶・菓子の小売・卸売、飲食店経営を担っており、主力商品の和スイーツ「喜久福」や「ずんだシェイク」、飲食店「喜久水庵」でもおなじみです。
井ヶ田社長は、自身の転機となったのは、10年前に「秋保ヴィレッジ」をオープンしたことと語りました。秋保ヴィレッジは秋保温泉の近くに開設した複合施設で、480 坪の店舗では農産物やお茶・お菓子の販売と、フードコートを併設しています。
「観光地への出店を模索して太白区秋保に11,500 坪の用地を確保した当時、周囲の耕作放棄地が気にかかりました。そこで、魅力を増すには周辺を元気づけなければと、地元農産物の直売を発案しました。農家さんにとって、直売だと市場に出せない不揃い品や少量生産の野菜なども出荷できる上、流通経費を削減できるというメリットがあります。市場に出荷するより多少手間はかかるけれど、その分、収益が増えるのです。そうした魅力を感じていただき、当初60軒だった出荷農家は今や250軒に増え、新規就農者も目立ちます」と井ケ田社長。
施設全体の売上は年間 6億円から8億5000万円に成長。仙台とゆかりのある愛媛県宇和島の産品を集めた「宇和島フェア」も毎年恒例となるほど好評です。
秋保地区にはここ数年の間に、ワイナリーやブルワリーの他、ジェラートショップやカフェなどが多数誕生しました。これほど集客施設や飲食店が増加する温泉地は全国的にも珍しいと言われますが、それを牽引したのが秋保ヴィレッジの存在です。
「先代社長は雇用と納税以外で地域貢献をしたいと言っていました。秋保ヴィレッジの取り組みを経験したことで、SDGsにつながるこの理念を、会社を引き継いだ当時よりもいま非常に実感しています」と語ります。
現在は2027 年に白石市に誕生する「道の駅」での物販と産直販売を受託し、秋保ヴィレッジで得た経験を活かしながら準備を進めているそうです。
超高齢社会における「地域住民×専門職」
《アクアビット・ファクトリー株式会社 代表取締役 蓬田裕樹氏》

「アクアビット・ファクトリー株式会社」は、デイハウス(介護予防教室)や認知症カフェ(ハッピーカフェ)の取り組みについて、法人の枠を超えた専門職集団が活躍している点や地域の「ハブ」としての機能を発揮している点が「世間よし」として高く評価され、令和4年度「仙台『四方よし』企業大賞」を受賞しています。
介護・医療保険事業を展開する同社は宮城野区幸町エリアの2拠点、若林区沖野エリアと来年できる同区遠見塚エリアの各1拠点、計4拠点・11事業所から成ります。「FUN TO CARE, FUN TO LIFE(ケアに楽しさを 人生に喜びを)」をコンセプトとし事業を展開しています。
蓬田社長は「最も実現したいのは、だれもが未来を選び取れること」と明言します。「この超高齢化社会、仙台市でも2040 年には高齢者が30% 近くを占めると予想され、予防と初期対応の重要性が増しているため、これまでとは異なる深い視点での仕組みが求められます。理学療法士、作業療法士等の様々な専門職や地域資源(人・コト・情報など)と日常的に出会える機会をつくり、それぞれがやりがいをもって活躍できるように、そしてすべての人において、必要な「選択肢」が必要なときに選べるようにすることを目指しています」。
蓬田社長の思いを具現化したのが、地域の人が集って要介護状態を予防する「デイハウス」や認知症の方やその家族が参加できる「ハッピーカフェ」です。「東日本大震災発生時、介護や福祉の専門職として被災者を支援する活動を続けてきた中から生まれた事業です。いずれも各専門職が継続的に関わり、地域住民が自発的に参加できるよう信頼を得ながらアシストしています。」
「福祉とは、人の人生や社会をデザインすること。今後はグループホームや包括ケアステーションの運営のほか、コンサルティングやフランチャイズ事業も手掛けていきます。またNPO 法人スポットライトを立ち上げて、こども食堂などの展開も計画。互いの事業がサポートし合い、コラボし合う状況を作りたいと考えています」。
「ひととちいきのミライをゆたかにする」
《株式会社ユーメディア 代表取締役 今野均氏》
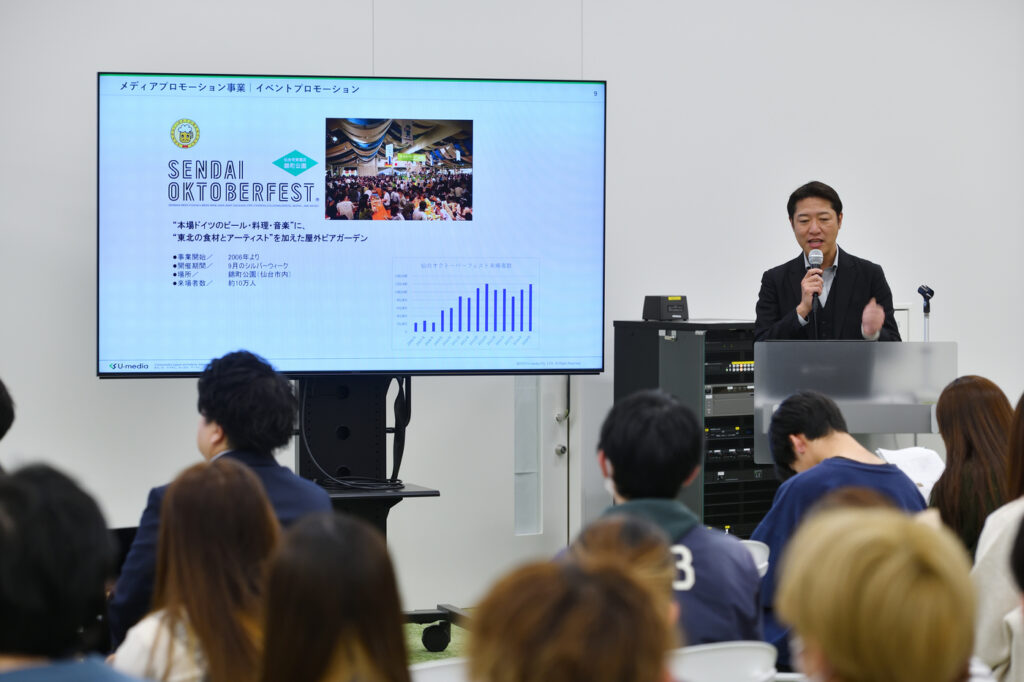
「株式会社ユーメディア」は、自社主催イベント「仙台オクトーバーフェスト」や「働き方を誇れる成長企業No.1」を目指した取り組みについて、仙台・宮城の魅力が実感でき、売り手も買い手も元気になるイベントの提供が「世間よし」、社員参画型の働き方改革の実践が「働き手よし」として高く評価され、平成30年度「仙台『四方よし』企業大賞」において優秀賞を受賞しました。
同社は、広告印刷やホームページ制作、イベントの企画運営を手掛け、グループ会社では『せんだいタウン情報S-style』『Kappo仙台闊歩』などの自社メディアも持っています。
今野社長が注力するのは人づくり、組織づくり。「人手不足で悩む企業や団体に向けては我々の知見を提案し、地域課題解決のためには地域の魅力を高める取り組みを強化したい。〈ひととちいきのミライをゆたかにする〉というミッションに基づいて事業を展開しています」。
今野社長が事業を承継した2011年、東日本大震災を機に会社の存在意義を見つめなおして思いを新たにしたと言います。その心意気はまずは震災半年後、青葉区の錦町公園で開催したビールの祭典「仙台オクトーバーフェスト」に表れました。
「毎年12万人を集客する自主事業ですが、ドイツからビールを輸入する都合上、3月中に実施か否かを判断しなければなりませんでした。まだ印刷工場も稼働できない頃でしたが、開催を決めました。おそらく震災後の市内で、民間主導でアルコールを提供した初のイベント。非難されるのも覚悟しましたが、みなさん楽しんでくれて、これを待っていた、またみんなで頑張ろうという気持ちになったと声をかけていただきました。この年の来場者数と売上は過去最高。少し背伸びすることで地域貢献ができると実感しました」。
その後は、定禅寺通りのエリアマネジメント会社も起業。杜の都を象徴する通りの魅力化を図り、市役所前広場にカフェレストラン「Route 227s’ Cafe」を(株)ハミングバードとの共同経営によりオープンしました。227という数字は東北にある市町村の数。各地の食材を使ったメニューを提供しています。
「事業を進める働き手自身がワクワクしながら仕事をするには、人と組織の開発が必要です。事業が成功すれば関係する人たちへの影響力が増し、自らも高めなくてはならない。また、働きやすい職場環境を提供すれば、大変だけれど乗り越えてやっていこうという意欲や満足感が生まれ、会社としての発展につながる。そんな良い循環が重要だと考えています」。
最後のパートでは、東北学院大学地域総合学科政策デザイン学科 2 年生の学生チームが、保育・福祉事業を展開する「株式会社ミツイ」と、公共施設の建築設計監理を行う「株式会社関・空間設計」を対象に企業研究を行い、その成果を発表しました。各社の理念や事業内容、職場環境、そして企業としての魅力と、仙台「四方よし」受賞企業にふさわしい特徴を学生の視点からまとめ、プレゼンテーションしました。
「株式会社ミツイ」の取材を担当した学生からは同社について、「顧客満足度を向上させるために社員満足度を追求している。現場の社員がよい、必要だと考えた事案は実現できるよう柔軟にサポートし、ひいてはそれが社会問題の解決にもつながっている」と分析。「働き手よし」の事例として保育士が自分の子どもを自分の勤務する園で保育する子連れ出勤の実践を紹介しました。

これについて同社HRシステム事業部の生田目将太朗ゼネラルマネージャーは「子連れ出勤のように、現場と調整しながら前例を作り、社会の変革をめざしている点をクローズアップしてくれた。働きやすくやりがいがある職場だと感じてもらえたらうれしい」と感想を述べました。

続いて、「株式会社関・空間設計」の取材を担当した学生チームは、同社の理念「スピリット・オブ・プレイス」に共感を示し、場所の持つ魅力を継承しつつ、建築を通して社会貢献する姿勢に着目しました。職場環境がスピーディーに改革された背景を取材し、「30数人と少人数であることから社員間のコミュニケーションが濃密で、個人のスキルアップが早い。多彩な建築を担当する可能性も開ける。自ら計画する海外研修制度は魅力的で、帰国後のレベルアップにつながっている」と紹介しました。

同社 岩根敦取締役設計監理部長は、「今回は学生の皆さんに当社を知ってもらうよい機会となった。当社はボトムアップ型で個人のスキルを発揮する自由度が高い。働く環境を向上させることが、働き手の高いパフォーマンスを引き出す」とし、同社が大切にする「ずっと一緒に考えよう」「建築を通して、社会のあり方を考える」などの「12の言葉」を紹介してくれました。

最後に和田教授は、「今日お話しいただいた5社はいずれも地域全体の未来を視野に入れた、高度な事業を展開している。一言一言が学生の心に刺さったのではないか。そしておそらく各社の社員は自らの職場について、今日会社を代表してお話ししてくださった方と同じように理解し、語ることができるだろう。そうした企業が地元仙台にあることをしっかり胸に刻んでほしい。また、本セミナーを通じて、企業、行政、そして大学が連携し地域政策をデザインしていくことが大切であると感じてもらえたのではないか」と結びました。
